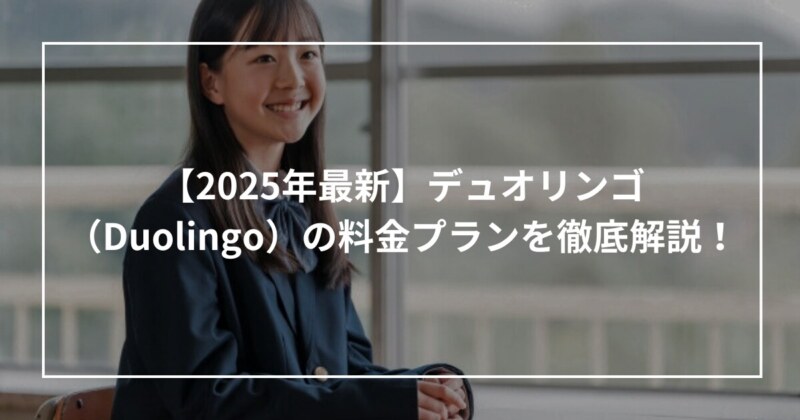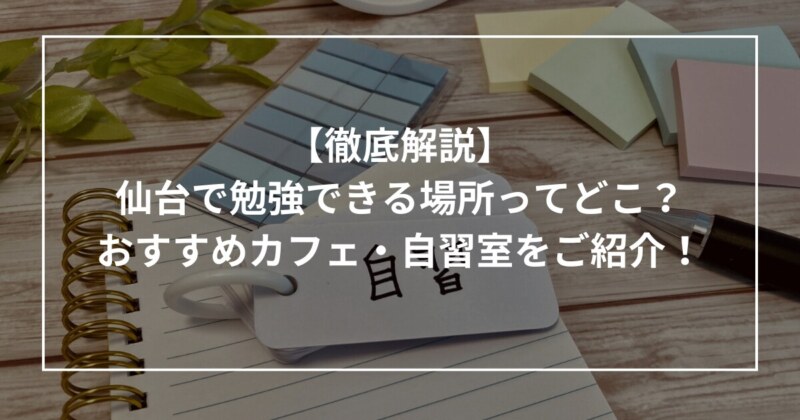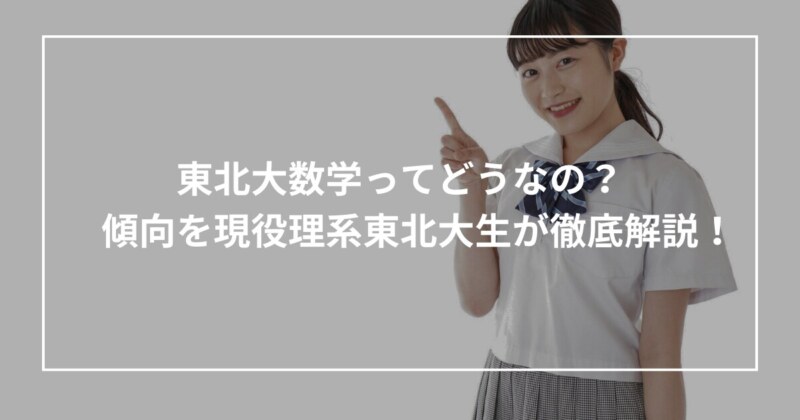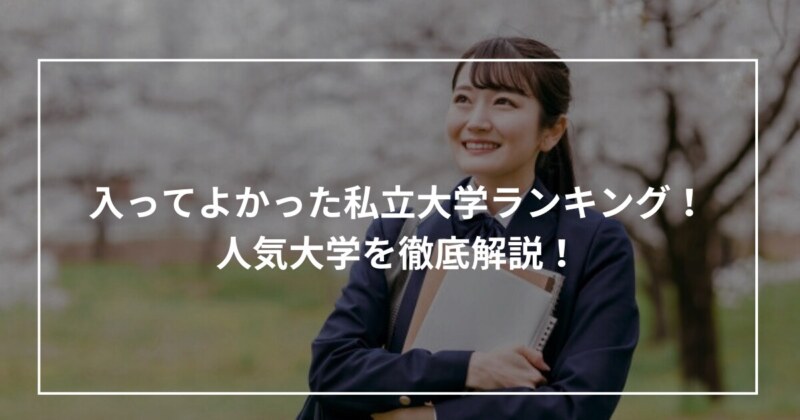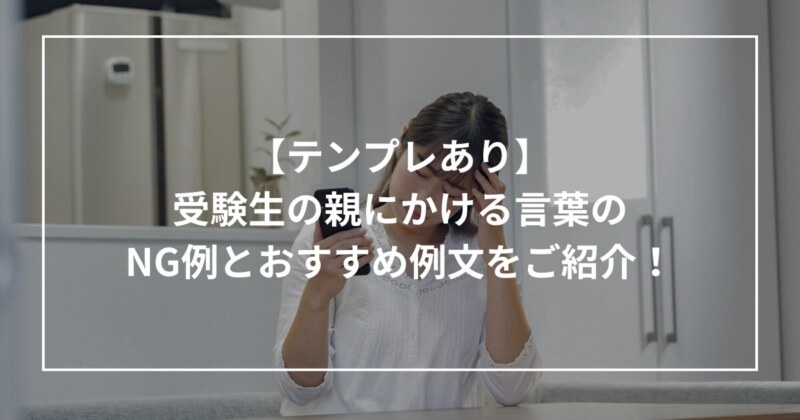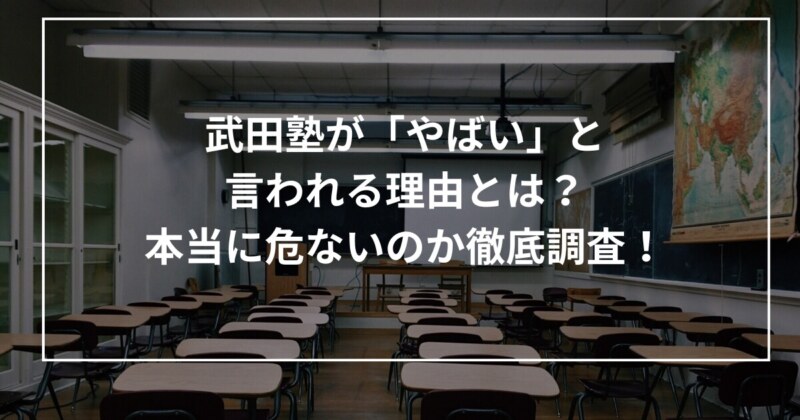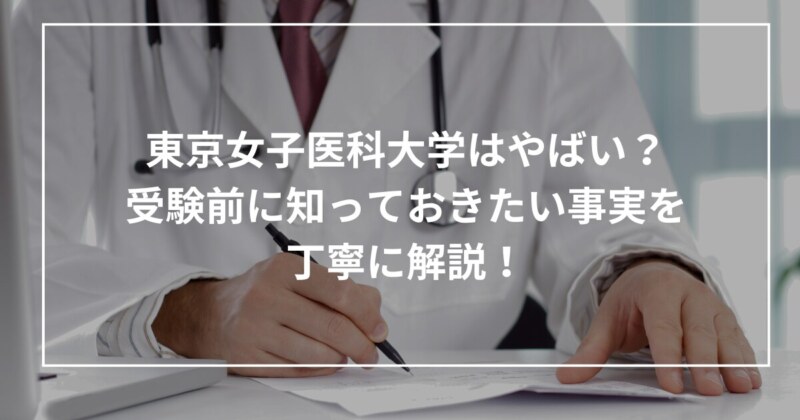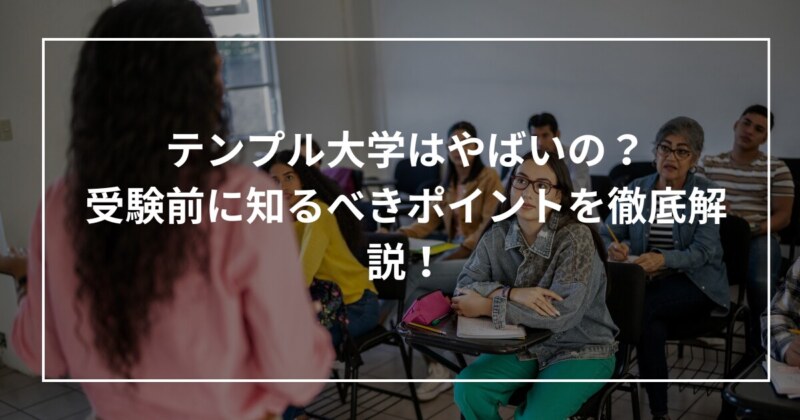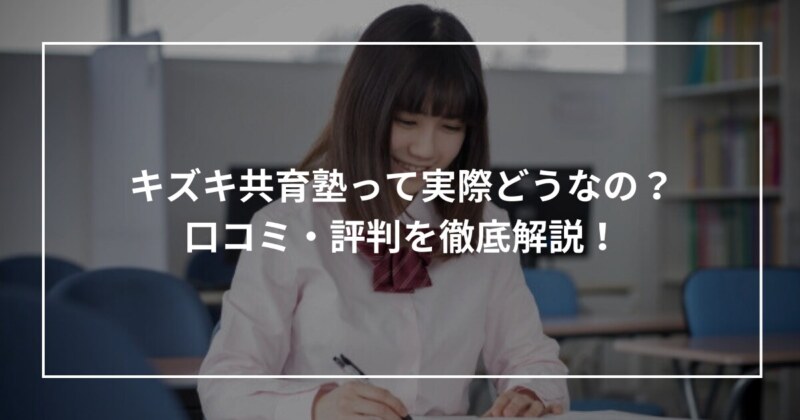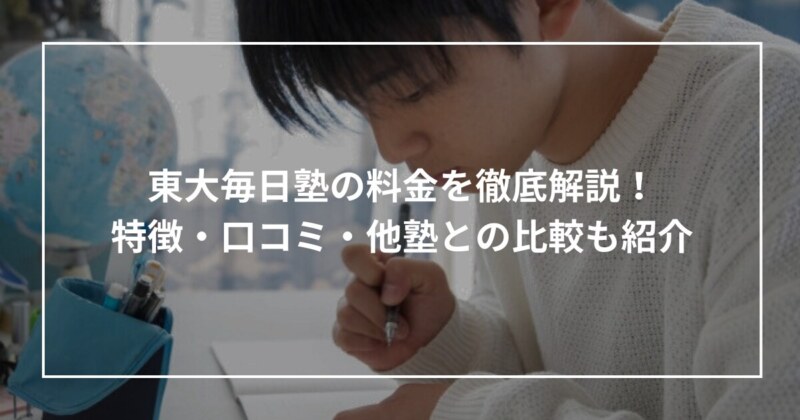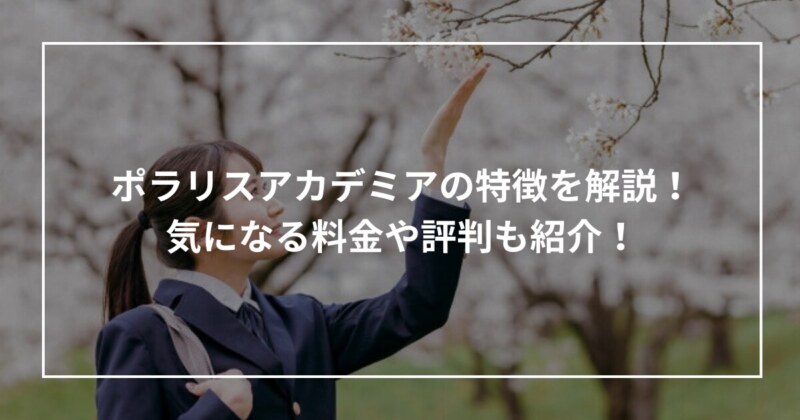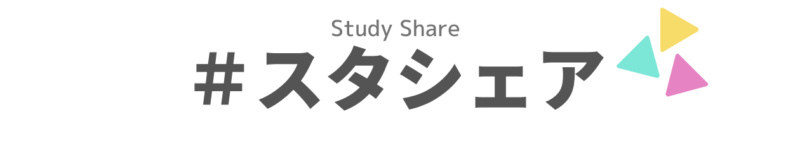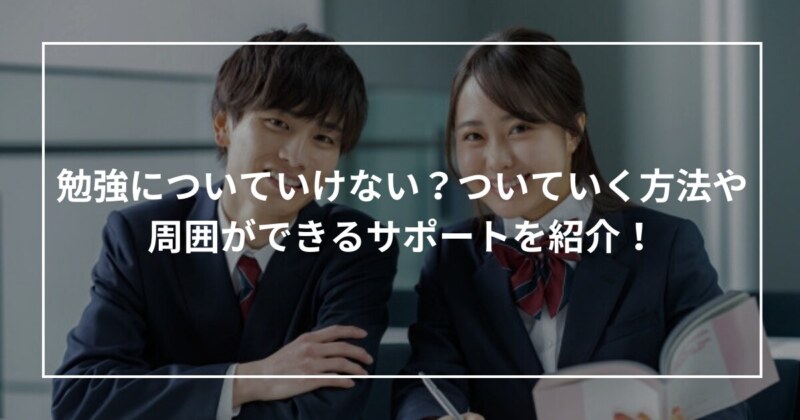学校の勉強についていけない
授業で何を言っているのか分からない
こんなお悩みはありませんか?
本記事では、勉強についていけない原因、勉強についていくための対処法や保護者のサポート方法について解説します。
「勉強についていけない」と悩んでいる人必見です!
- 中学校や高校は自宅学習を前提として授業が進むので、学校以外での学習が必須!
- つまづいた箇所までさかのぼり、計画的に学習をリスタートしよう。
- 分からない部分はすぐに解決することで、勉強についていけるようになる!

独学で東北大学医学部に現役合格。指導経験の中で、“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」、東北大専門塾「Elevate」を創設。全国の受験生を支援している。
詳しくはこちら
現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。

東北大学教育学部在学中、自身の浪人体験から、モチベーション支援や学習戦略の大切さに気付き、オンライン学習管理塾「168塾」と東北大専門塾「Elevate」を共同創設し、IT技術を活用した学習管理で全国の受験生を支援している。
もっと詳しく
現在は教育メディア「#スタシェア」の運営を行いながら、プロダクト開発と現場支援を両輪に、学びの選択肢と質の向上に取り組む。
勉強についていけない原因9選

新しいステージへと進級すると「勉強についていけない」と感じる人が多くいます。
小学校から中学校、または中学校から高校へとステージが進むことで様々な変化が生じることがその原因といえるでしょう。
ここでは、勉強についていけない原因を9つにわけ分析します。
1.部活動や習い事で忙しい
2.学習内容が多い
3.学習内容が難しい
4.学習進度が早い
5.学習習慣が身についていない
6.生活習慣が乱れている
7.勉強の仕方が分からない
8.勉強に苦手意識がある
9.集中力が続かない
1.部活動や習い事で忙しい
部活動や習い事で学校が終わった後のスケジュールが埋まってしまい、勉強時間が確保できなくなることがあります。
特に試合や発表会の前などは、練習が増えて帰宅時間が遅くなり疲労がたまることで、勉強をするエネルギーが残っていないという人が多いです。
その結果、授業で習った内容が定着せず、どんどんと理解が追いつかなくなってしまいます。
2.学習内容が多い
中学校以降は小学校までと異なり、教科が細かく分かれ、各教科ごとに多くの内容を学習するようになります。
特に、高校生になると科目数が一気に増え、覚えるべき範囲が多岐にわたるため、復習が追いつかなくなることがあります。
3.学習内容が難しい
学年が上がるにつれ、学習内容はより抽象的で複雑になり、一度つまずくと追いつけなくなることがあります。
例えば、数学では公式Aを理解していないと公式Bが使えない、英語では文法Aと文法B文法Cを理解していないと長文読解ができない、というように、前単元の積み重ねが求められる教科もあります。
一度つまづいてしまいと、雪だるま式に勉強についていけない状態になってしまいがちです。
4.学習進度が早い
学校の授業の進度が速いことが原因で授業についていけなくなることもあります。
特に集団授業では、1人1人の完璧な理解ができていない状態でも容赦なく次の単元に進んでしまうので、気づいたときには「勉強についていけない」という状態になってしまっていることも。
授業での疑問はその日のうちに解決しないと、どんどん置いていかれる可能性が高まります。
5.学習習慣が身についていない
日々の勉強習慣が身についていないと、学んだことを定着させるのが難しくなり、結果として「勉強についていけない」という状態になってしまいます。
6.生活習慣が乱れている
睡眠不足や食生活の乱れなど、生活習慣が整っていないことで集中力が低下し、勉強に対する意欲が削がれることが、勉強についていけない原因になることもあります。
睡眠時間が短く授業中に眠くなってしまうなど、授業内容を十分に理解できない日々が続くことで、勉強についていけなくなってしまいます。
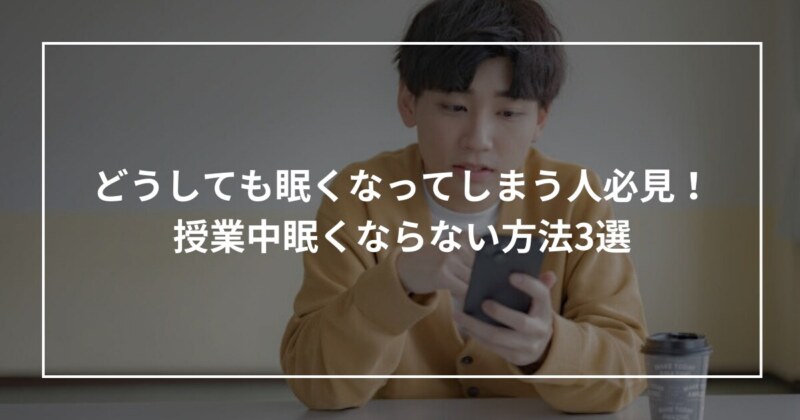
7.勉強の仕方が分からない
「時間をかけて勉強をしているのに、授業についていけない」と感じている人は、勉強の仕方そのものに問題がある可能性があります。
効率的な方法で学習に取り組まないと、ただ時間だけがかかり結果に結びつきにくくなってしまいます。インプットとアウトプットを交互に行い、効率のよい方法で学習に取り組むことをおススメします。
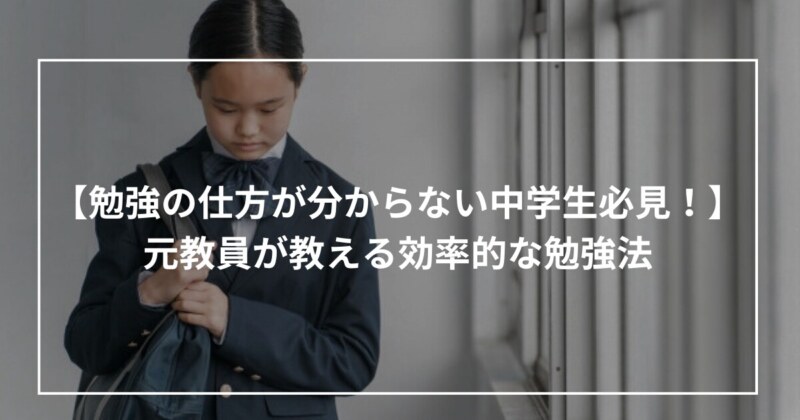
8.勉強に苦手意識がある
「自分は勉強が苦手」と思い込んでしまうと、学習へのモチベーションが下がり、努力する前に「やりたくない」と諦めてしまう人がいます。
勉強はやれば必ずできるようになりますので、あきらめないで取り組みましょう。
9.集中力が続かない
勉強しようと思っても、すぐに気が散ってしまい、長時間机に向かうことができない場合があります。
特にスマホやゲームなどの誘惑が多い環境では、勉強に集中しづらくなります。
集中力が続かない人は学校の自習室や図書館など、「勉強以外できない場所」で学習することをおススメします。
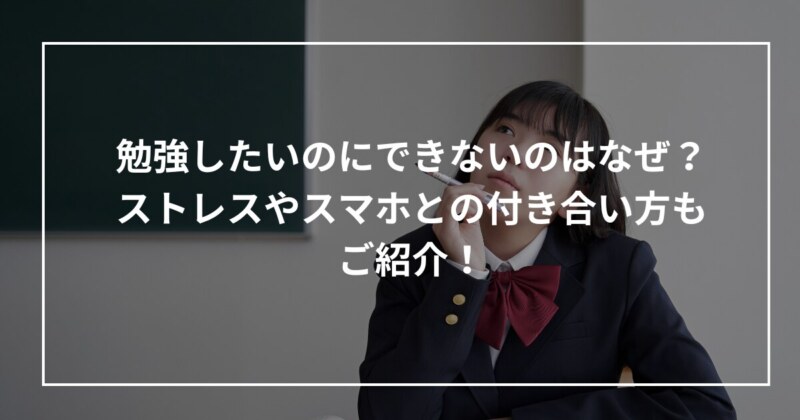
勉強についていくための対処法6選

「自分は今勉強についていけてない」と感じたときこそ、改善のチャンス!
自分ができそうなもの・自分にあっていると感じる対処法から、ぜひ試してみてください。
1.分かるところまでさかのぼり学習をリスタート
2.基礎を固める
3.授業の復習はその日のうちに行う
4.分からない部分はすぐに解決する
5.自分に合った学習スタイルを見つける
6.計画的に勉強を進める
1.分かるところまでさかのぼり学習をリスタート
理解できない部分があれば、無理に次へ進むのではなく一度基本に戻って学習し直すことが大切です。
特に数学や英語などの積み上げ型の科目は、基礎ができていないと応用が理解できなくなります。学年を気にするのではなく、自分の理解度に焦点を当て思い切ってさかのぼりましょう。

高校2年生なのに中学1年生の内容が分かってないなんて恥ずかしくて言えない…



さかのぼることは恥ずかしいことではないですよ!
それよりも理解できるようになることの方がよっぽど大事!
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」
2.基礎を固める
日々の学習で基本的な知識や公式の理解にあてる時間に重点をおいてみましょう。
それを使いこなせるように繰り返し学習することで、発展問題・応用問題にも対応できるよう力が身に付きます。
3.授業の復習はその日のうちに行う
学習内容を記憶として定着させるためには、その日のうちに復習することが最も重要です。
忙しくても、5分だけその日の学習内容にあたる問題に取り組むことで、学習の定着度がぐんとアップします。



高校生は通学のスキマ時間で学習アプリを使うのもおススメ!
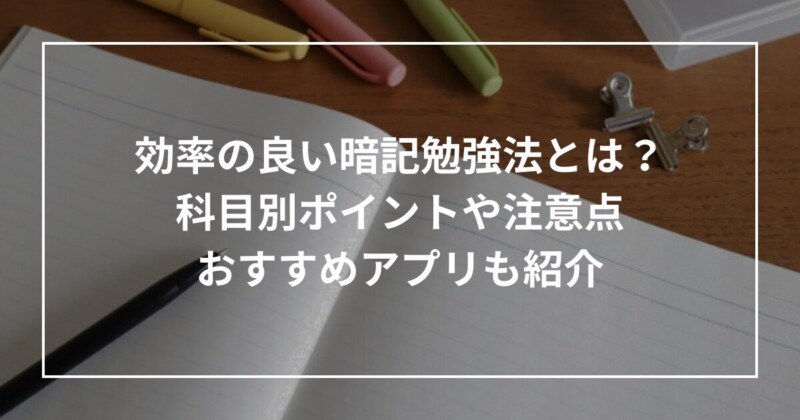
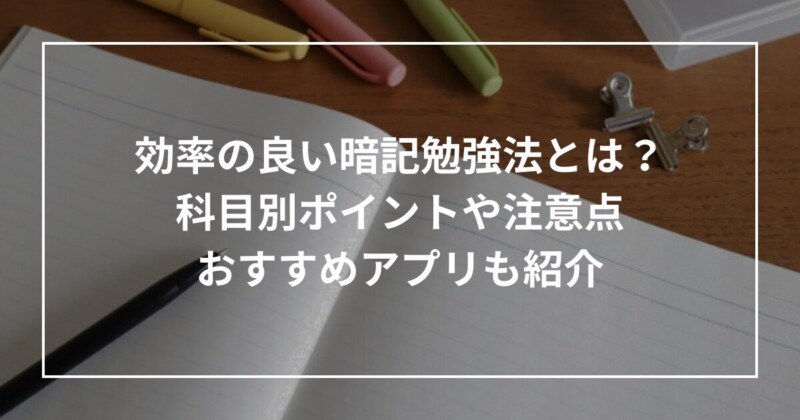
4.分からない部分はすぐに解決する
疑問を抱えたままにしないことが大切です。
「なぜこの答えなのか分からない」という疑問は、時間が経つにつれ、疑問に思っていたことさえも忘れてしまいます。そうなると、①疑問点を探す→②疑問点を解消する、と勉強についていくために行わなけれなならないことが増え、学習が億劫で嫌になってしまう可能性が高くなります。
先生に質問したり、参考書や教科書を確認するなどして、疑問点はその日のうちに解決しましょう。
5.自分に合った学習スタイルを見つける
書いて覚える、声に出して覚える、視覚的に学ぶなど、人によって効果的な学習方法は異なります。
また、バス通学で参考書を読む時間がある人もいれば、自転車や徒歩通学の人など、学習環境も様々です。
試行錯誤しながら、自分の性格やライフスタイルに合った勉強法を見つけることが大切です。


一方で、「勉強したつもりになるなかなか身につかない勉強法」だけは避けたいところ。
限られた時間を最大限効率的に学習に使いましょう。
6.計画的に勉強を進める
分からなかった箇所の学習が追い付き、勉強についていけるようになったら、今度は「またついていけなくなった」という状態にならぬよう、現状の授業速度に合わせ学習を進めていかなければなりません。
例えば、「1日に問題集を2ページ進める」といった具合に、毎日の生活のなかで負担になりすぎず、細かすぎず、継続しやすい目標をたてて計画的に進めることで、無理なく学習を続けることができますよ。
【おすすめオンライン塾】
毎日の学習計画から進捗管理まで、
すべてプロにお任せできるオンライン学習管理塾「168塾」
専用アプリで24時間サポートし、勉強の習慣化と成績アップを実現します。
「ゼロから逆転合格できる」
1日単位で勉強を管理
無料相談は公式LINEから
【保護者向け】勉強についていけない子どものサポート方法


子どもが学校の勉強についていけないようだけどどうしたらよいでしょうか…



親としては心配になりますよね。
でも勉強は正しい方法で取り組めば絶対にできるようになります!
心配しすぎず、手を打ってあげましょう。
自宅でできる効果的なサポート方法
まず保護者の方に知っておいてほしいことが、否定的な声がけをしないようにということです。
例えば…
「勉強おいつけてないの?何やってるの?遊んでばかりいるのがダメなんじゃないの?」
「追いつけるように早くがんばって勉強しなさい!」
「スマホとりあげるよ!」
ついつい言いたくなっていませんか?
保護者の方の気持ちはよく分かります。でも子どもが自身で「勉強についていけない」と感じ、何とかしようとしているところに追い打ちをかけても、良い結果にはつながりにくいと言えます。
まずは、子どと一緒に勉強しやすい環境や生活習慣を整え、学習習慣が身につくようサポートをしてあげましょう。また、「できていること」「できるようになったこと」に目を向けてあげてください。
反抗期でなかなか子どもが言うことを聞かない場合もあると思います。
しかし、直接的な声掛けや関わりがなくても、子どもは「親が自分のためにしてくれていること」を敏感に察しますので、子どもの困りごとを共に解決したいんだ、というスタンスでお子様に向き合ってあげてください。
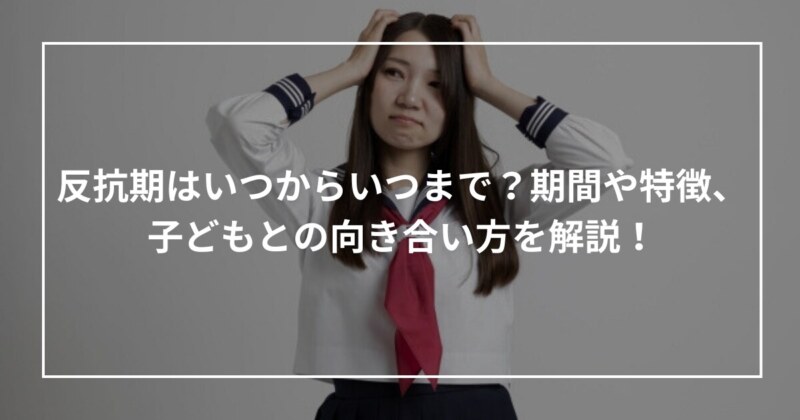
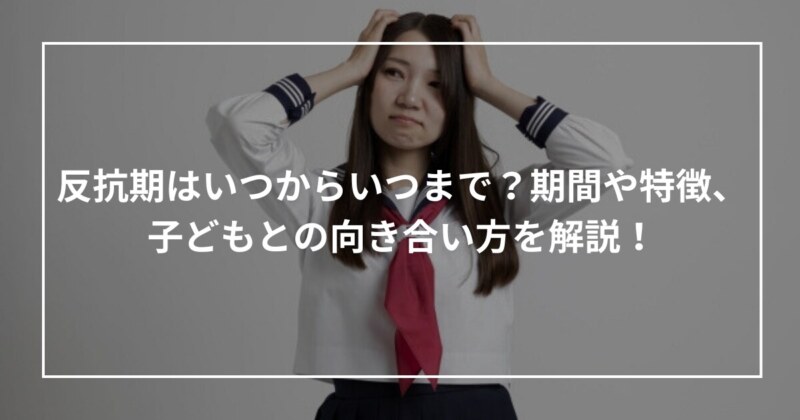
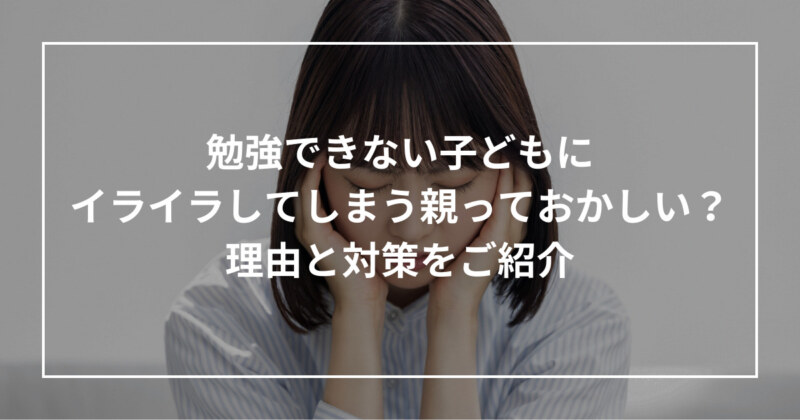
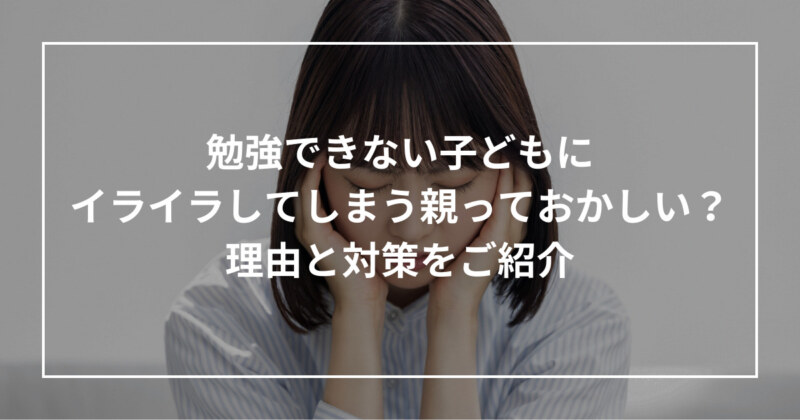
小さな成功体験を積み重ねる
簡単な問題から取り組むことで、自信をつけ、モチベーションを高めることができます。
特に勉強に対して苦手意識があるお子様や、拒否反応を示すお子様には、思いきってさかのぼった学習が有効です。
継続的な学習習慣を身につける
毎日少しずつでも勉強を続け学習の習慣が身につくことで、勉強への苦手意識が薄れ、理解度の向上につながります。小中学生のお子さんをもつご家庭におススメなのは家庭での学習時間を親子で話し合って決めること。
「学校から帰ってきてから夕食までの30分間は問題集をする」
→「子どもがお風呂に入っている間に保護者が○つけをする」
→「次の日の朝登校前の30分で間違えたところを解きなおす」
というように、毎日の生活の中で学習をルーティーンとして組み込むことをおススメします。
周りのサポートを活用する
そうは言ってもうちの子、親の言うことなんかまったく聞かない…
反抗期の時期ともちょうど重なるので、そうしたご家庭も多いのではないでしょうか。
そういう場合は、学校の先生や塾、家庭教師など、周囲のサポートに頼ることも一つの手です。



親の言うことは聞かないが塾の先生の言うことは聞くというケースは、結構多いです。
「勉強についていけない」と感じたら、学習習慣の形成からゼロからサポートする168塾がおすすめ!
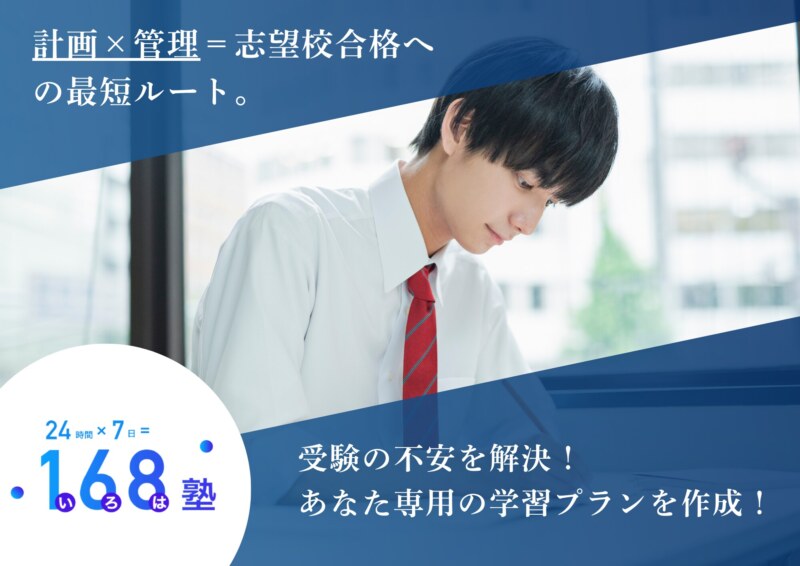
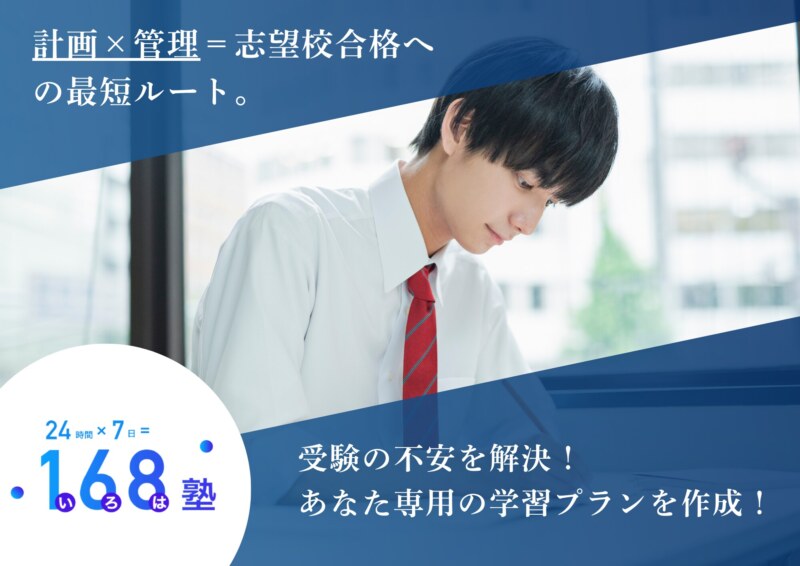



大学受験がとても不安‥



このままで本当に合格できるのかな…
このような悩みを抱える方はいませんか?
そんな方には、徹底した学習サポートが強みの168塾がおすすめです!
生徒一人ひとり、勉強の悩みや改善点はそれぞれ違います
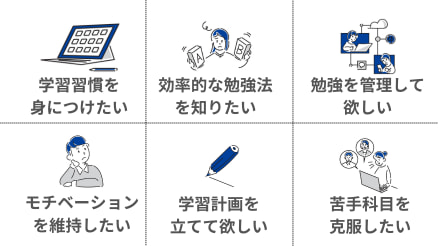
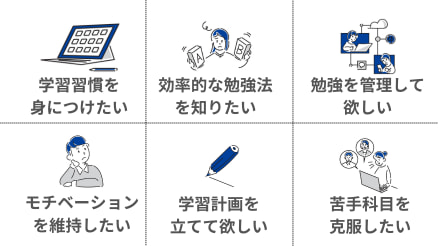
168塾では、受験のプロである担当コーチが、いま抱えているお悩みや勉強の状況を丁寧にヒアリングし最適な学習プランをご提案します。
また塾生専用の学習進捗確認シート、LINEを用いた毎日の進捗管理、担当コーチとの振り返り面談をおこない、勉強の質も高めていきます。
正しい勉強のやり方で、勉強量と勉強の質を高めていけば成績を飛躍的に向上させることが可能です。
168塾では現在、オンラインで無料受験相談も行っています。気になる方や相談したいことがある方はぜひ気軽にお申し込みくださいね!
\ 毎月先着30名様限定/
\ まずは168塾のことを知る /