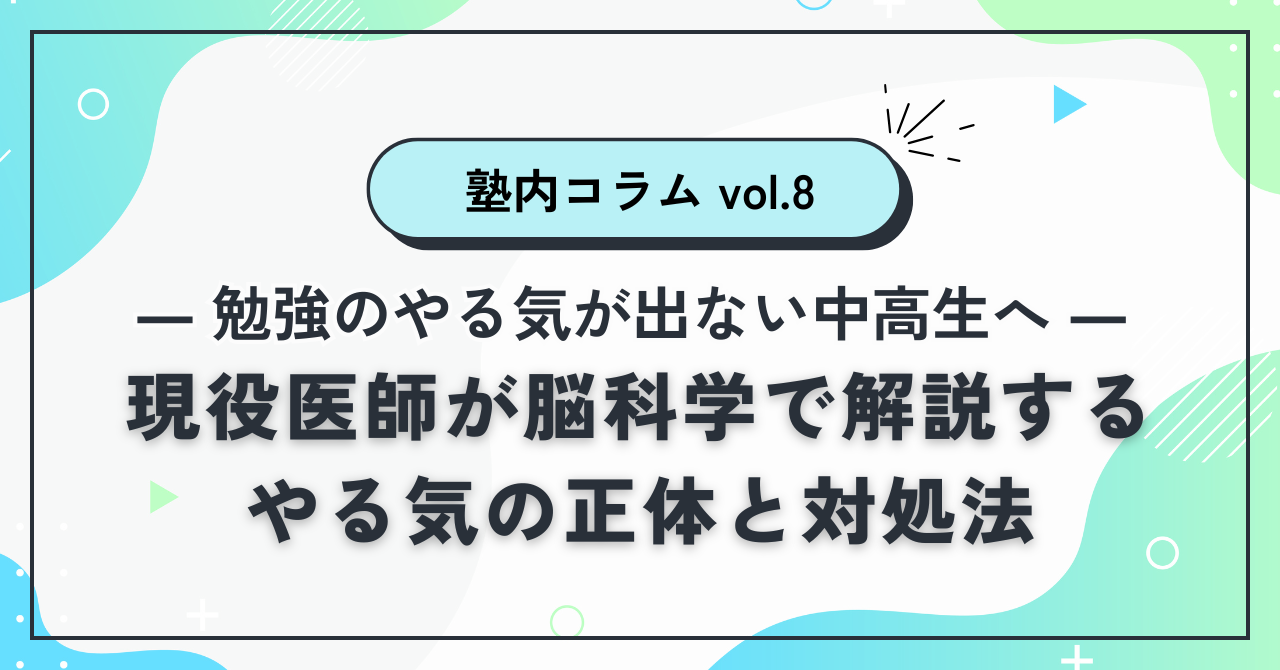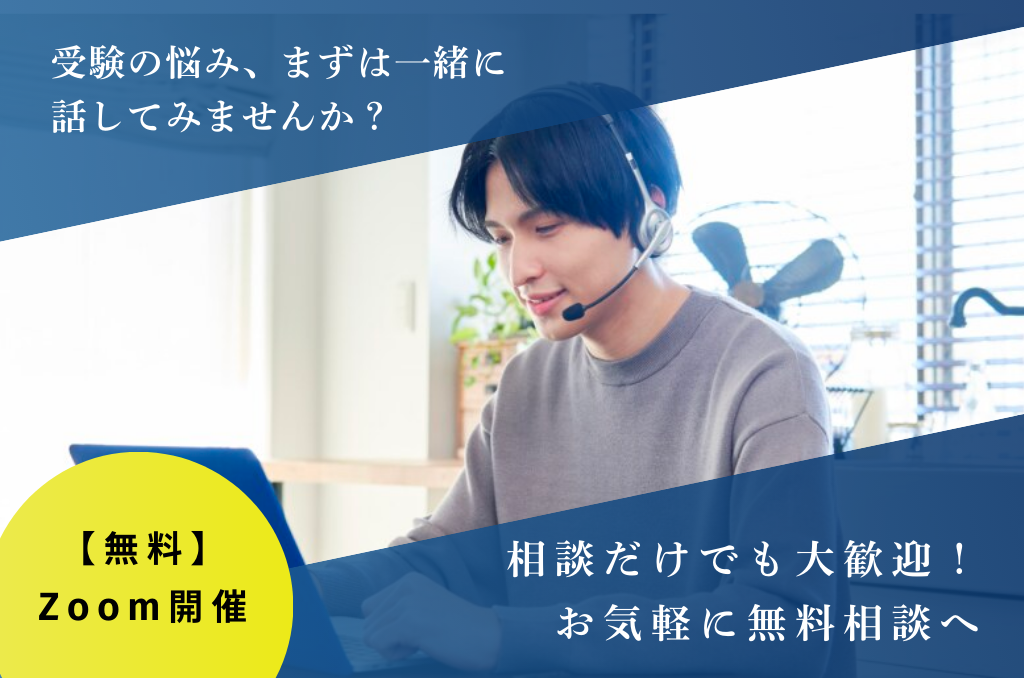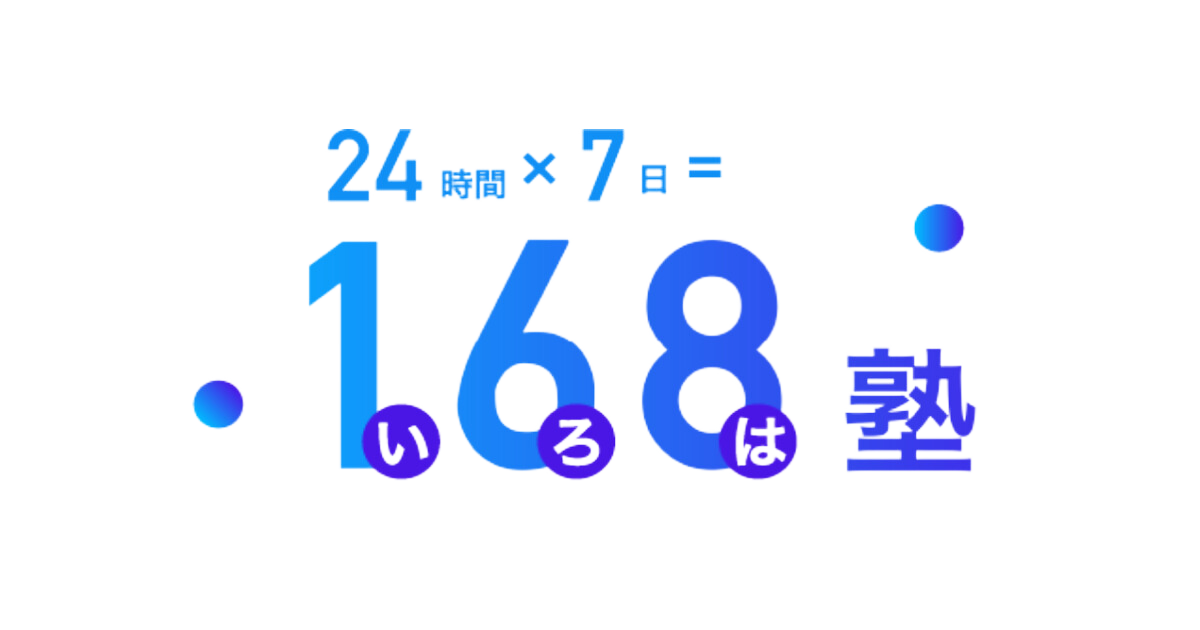スマホ・SNS時代の子どもたちに必要な「学びの力」とは?
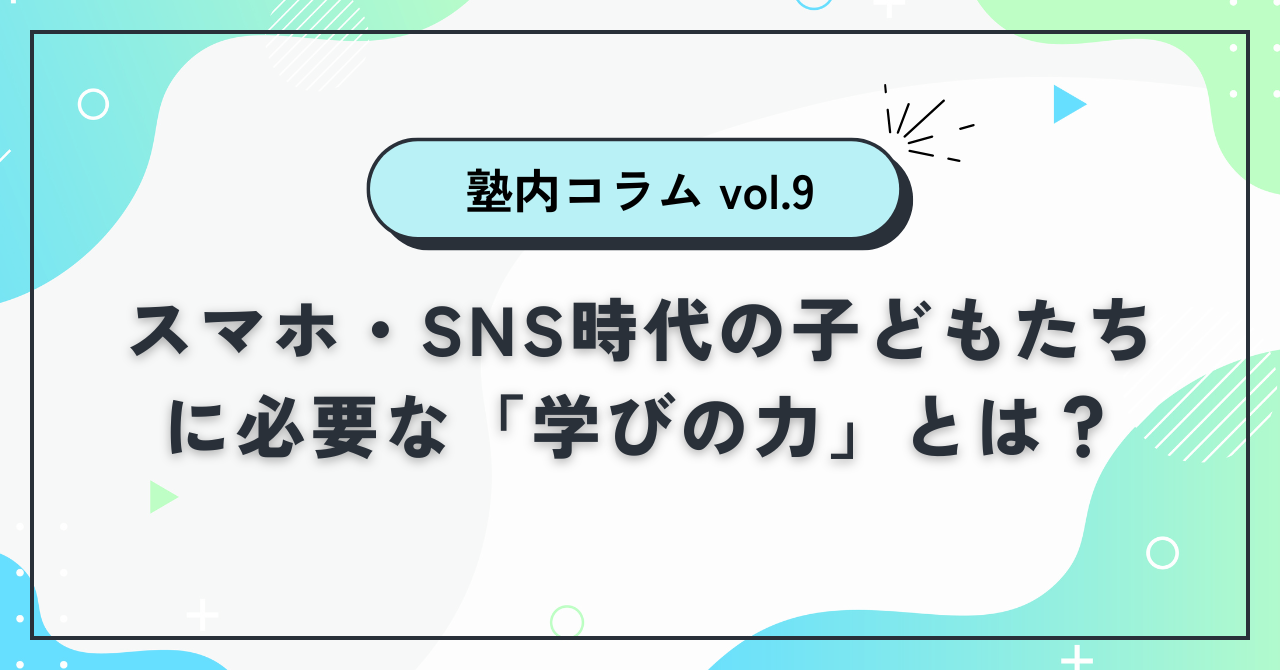

独学で東北大学医学部に現役合格。塾講師として指導を行う中“塾外の時間”の使い方こそが成績向上の鍵だと気づき、1週間=168時間に着目したオンライン学習管理塾「168塾」を創設。全国の受験生を支援している。
詳しくはこちら
現在は東北大学大学院加齢医学研究所にて、脳科学と教育を融合させた研究を行うと同時に、東北大学病院 認知症外来で診療に携わる現役医師でもある。学術と現場の両視点から、「自走力を育む学習法」の確立を目指し、受験にとどまらない“生きるための学び”を提唱。
令和の子どもたちは、保護者世代が子どもだった頃とはまったく違う環境で育っています。
スマートフォンやSNS、動画アプリ、オンライン教材——。
いつでもどこでも情報にアクセスできる便利な時代だからこそ、
「集中力の分散」や「時間の浪費」という新しい課題も生まれています。
文部科学省の調査(令和5年度)によると、中高生のスマホ所有率は95%を超え、平日の平均利用時間は約3時間半。一方で、学習時間が2時間未満の層が全体の6割を占め、「スマホ時間」と「勉強時間」の逆転現象が顕著になっています。
スマホ時代に必要なのは、“時間を管理する力”
多くのご家庭で、お子さんが「ついスマホを見すぎてしまう」「宿題が後回しになってしまう」という悩みを耳にします。
実は、スマホやSNSそのものが悪いのではありません。
問題は、それを“どう使うか”という意識と習慣が育っていないことです。
心理学の研究では、人間は「通知」や「いいね」などの刺激により、脳内で報酬ホルモン(ドーパミン)が分泌されるため、スマホを手放せなくなる傾向があるとされています。
つまり、子どもにとってスマホは「小さなご褒美装置」のような存在なのです。
それは単なる「スマホ禁止」ではなく、
「時間をどう使うかを自分で決める練習」=自己管理力を育てる教育。
大人になっても必要な「自己管理能力」を育てる第一歩です。
教材があふれる今、“何を学ぶか”よりも“どう学ぶか”
YouTubeやオンライン教材、アプリ学習など、今は無料でも質の高い学習コンテンツが豊富にあります。
一昔前は、良質な教材に出会うには塾に通うしかありませんでした。
たとえば、同じ動画を見ても、
- ただ聞いて終わる子
- ノートにまとめ、翌日の勉強に活かす子
このように違いが出てきます。
この差は「情報を受け取る力」ではなく、情報を“咀嚼”して“行動に移す力”にあります。
情報があふれる時代だからこそ、“受け身の勉強”から“正しい情報を選択し行動する主体的な学び”への転換が求められています。
168塾が大切にしていること

私たちは、ただ成績向上や志望校合格をゴールにするのではなく、
子どもたちが自ら目標を持ち、計画的に努力・行動できる力を育てることを重視しています。
168塾では、独自開発した学習管理アプリ「168share」を使い、
毎日の学習内容・生活リズム・モチベーションを“見える化”。
さらに、週1回の面談では「先週の行動を振り返り、次週の計画を立てる」プロセスを繰り返すことで、
自己管理・自己分析のサイクルが自然と身につきます。
これは、スマホやSNSと向き合う上でも重要な「時間をコントロールする力」に直結します。
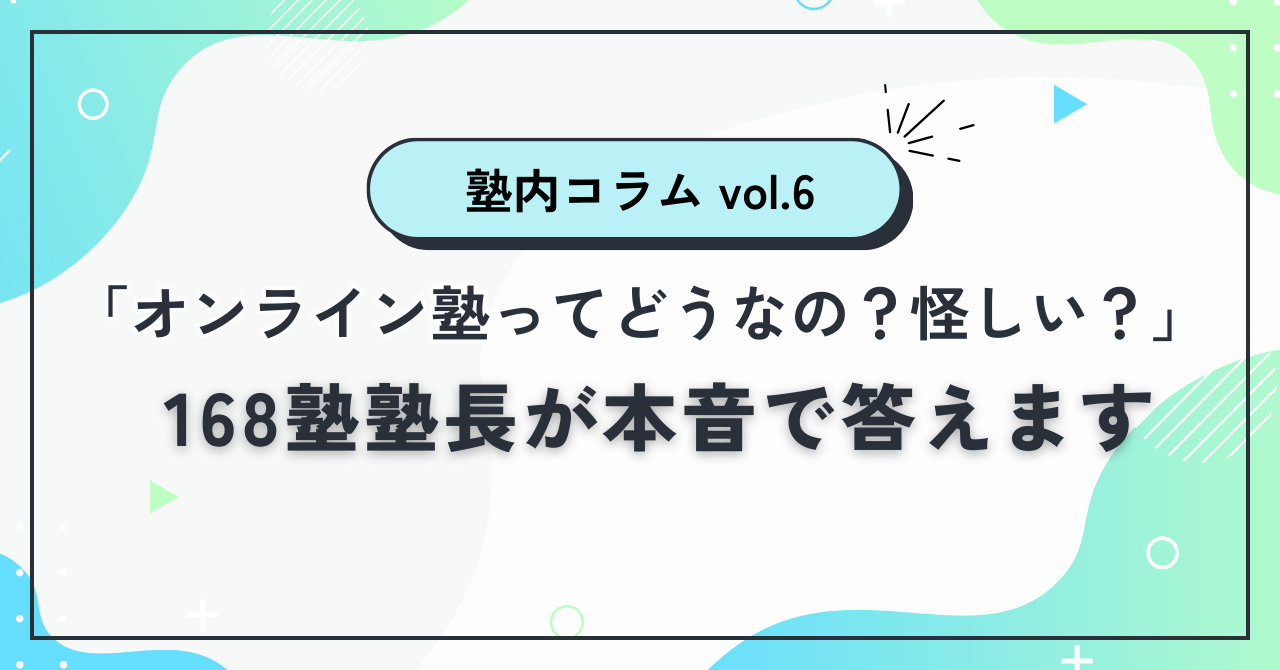
🌱 最後に
勉強の習慣が身についていない生徒さんと生活リズムを一緒に作っていくところから、
成績は良いけれど自信を持てない生徒さんが本番で結果を出せるように伴走するところまで。
168時間=1週間、丸ごと生徒に寄り添う「学習の伴走型サポート」が、
スマホ時代にこそ必要とされている教育の形だと私たちは考えています。
お子さまの「学び方を変えたい」「集中力や勉強習慣をつけたい」という方は、
ぜひ一度168塾の無料相談へご参加ください。
Contact
168塾の指導内容やサポート体制を詳しく知りたい方へ
168塾の指導内容やサポート体制を、詳しく知りたい方へ。
公式LINEなら「資料請求+無料学習アドバイス」が24時間いつでも受け取れます。
進路や勉強方法に迷っている方も、まずは気軽にご利用ください。