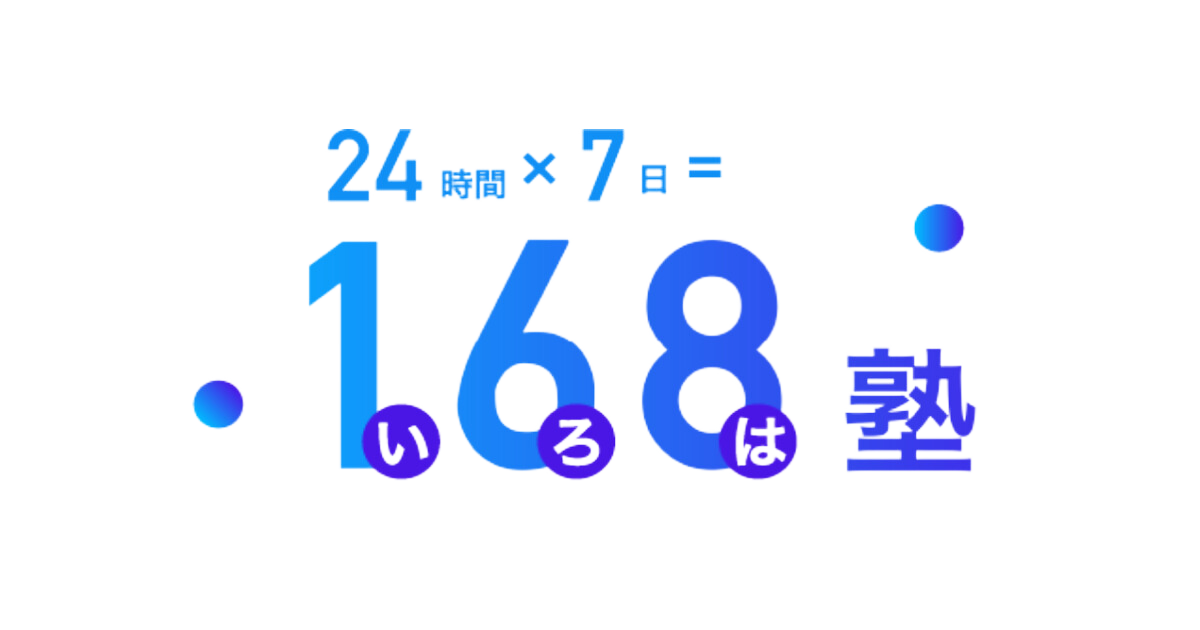【2025年最新】入門 英文解釈の技術70のレベルと使い方を徹底解説!

『入門英文解釈の技術70』(桐原書店)は、英文を構造から正確に読み解く力を養うための入門書です。
英文を「なんとなくの雰囲気」で読むのではなく、SVOCなどの構文に基づいて論理的に読み進める力を身につけることを目的としています。文法と単語を学んだあと、「長文が読めない…」と感じる人に最もおすすめの一冊です。
単語は覚えたのに訳せない、、、
そんな人におすすめしたい参考書です!
- 対象レベル
- 使い始める時期
- 他の参考書との違い
- 効率的な使い方・ノート例
- 学習スケジュール(2ヶ月モデル)
- 修了後のおすすめ参考書
入門 英文解釈の技術70のレベルは?
『入門 英文解釈の技術70』は、共通テスト〜MARCHレベルの英文を正確に読めるようになるための「構文読解の基礎」を扱う参考書です。
対象レベルの目安
| 偏差値 | 55〜60前後 |
|---|---|
| 英検 | 2級レベルの読解 |
| 対応大学 | 共通テスト・日東駒専・産近甲龍・MARCHの英文読解対策に有効 |
「英文法と英単語はひと通りやったけど、長文が読めない」と感じる人にちょうどよいレベル設計です。
どんな人に向いている?使い始める時期は?
- 英単語帳(シス単など)と英文法書(Next Stageなど)を一周した人
- 英語長文で「主語・述語・修飾」があいまいになって読めない人
- 構文把握を基礎から身につけたい人
- ポレポレなど難しめの参考書に入る前の準備をしたい人
英文法の基礎がまだ不安な人は…
▼ 先にやるべき参考書の例:
・大岩のいちばんはじめの英文法
・英文法をひとつひとつわかりやすく。
など基本的な文法事項を学習してから取り組みましょう。
文法・単語の基礎がある人にとっては最適な「構文解釈のスタートライン」
「読める=構造をつかめる」ようになる練習ができる
読解が苦手でも1日10分から始められる易しめの文章量
他の参考書との徹底比較!
同じシリーズ内での位置づけ(英文解釈の技術シリーズ)
『入門英文解釈の技術70』は、桐原書店の「英文解釈の技術シリーズ」の第2巻であり、構文読解の“スタートライン”に位置づけられています。
超入門→入門→基礎→発展と段階的にレベルアップできる構成になっています。
以下の表では、それぞれの巻の特徴やレベル感を比較しました。
| 参考書 | 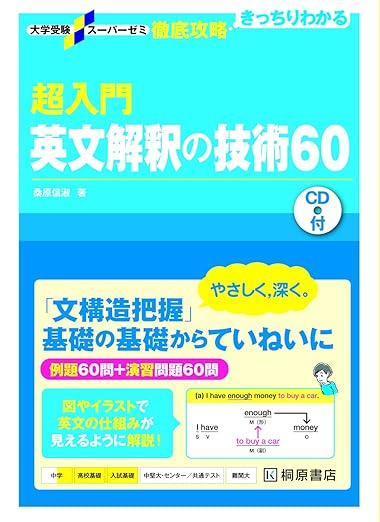 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 教材名 | 超入門英文解釈の技術60 | 入門英文解釈の技術70 | 基礎英文解釈の技術100 | 英文解釈の技術100 |
| 難易度 | ☆☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ |
| 対象者 | 英文解釈を始めて学ぶ人。高校英語の勉強を始めた人 | 文法・単語を終えた受験勉強を始めたての人 | MARCH・関関同立・中堅国公立志望 | 東大・京大・早慶など最難関志望 |
| 特徴 | 中学英語から復習したい人向けに非常に優しく書かれている | 全英文にSVOC表示。1文単位の精読練習に特化 | やや長めの文を扱い、構文+内容理解を求められる | 抽象度・論理性の高い構文が多数。記述対策向き |
『入門70』で構文の「読み方」を固め、志望校レベルに応じて次に進むというのが王道の流れです。
同じレベルの参考書は?違いは?
ここでは、『入門英文解釈の技術70』と同じようなレベル感(偏差値55〜60前後)の他の解釈書を比較します。
参考書 |  |  | .jpg) |
|---|---|---|---|
| 教材名 | 英文読解入門 基本はここだ!(代ゼミ 西きょうじ) | 入門英文解釈の技術70 | 入門英文問題精講(旺文社) |
| 難易度 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| 対象者 | 英文解釈をゼロから始めたい人 | 英文法・単語は済んでいるが構文に不安な人 | 短文で演習量を積みたい人 |
| 特徴 | 直訳→自然な日本語訳へと導く。SVOCの記載はなし。 | 全例文にSVOC表示あり。構造の見える化に特化 | 解説は簡潔だが、精読と構文の実戦練習向け |
- 「初めて構文解釈をやる」 → 『基本はここだ!』
- 「多くの短文を通して演習したい」→『入門英文問題精巧』
- 「文法・単語を終えて次の段階に進みたい」 → 『入門英文解釈の技術70』
入門 英文解釈の技術70の目次と構成
『入門英文解釈の技術70』は2部構成で、例題を通じて構文理解をしっかり定着させる仕組みです。
第1部:英文解釈の技術70(70テーマ)
中学〜高1レベルの文法項目を中心に、以下のような構文パターンを次のテーマに分けて学習します:
- SとVを発見する技術(主語と動詞を見抜く)
- 文の主要構成要素の把握(目的語・補語など)
- 等位接続詞の働き
- 時間関係の把握(時制・副詞句
- 従属節の見分け方
- 関係詞節の把握と省略
- 同格節の把握
- It is ~ that 節の構文
- 準動詞(不定詞・動名詞・分詞)の使い方
- with構文・比較構文・仮定法・倒置構文 など
例題 → 詳細解説(SVOC & and/or構文表示)→ 和訳 の見開き形式で構成されており、構造と訳を同時に把握しやすい設計です。
第2部:演習問題70
- 第1部と対応する70題の書き込み式演習
- 別冊『解説・解答』付きで、SVOCと訳を確認しながら学習可
- 付属CDまたは音声配布で音読・シャドーイングにも対応
実際の参考書の構成について
見開き1ページの構成で、学習テーマと問題文が最初に載っています。
解説が豊富で、最後に単語や熟語などの語句もまとめられているので非常に学習しやすいです!

特徴のまとめ
- 2部制:読解(インプット)→演習(アウトプット)で定着しやすい流れ
- 構文理解を短い例文(1テーマ1例文)で丁寧に学べる
- 演習も第1部と対応しているので、使った構文が定着しやすい
- 音声連携でリスニング・スピーキング練習にも活用可
このように、「構文を理解して読み解く力」を効率よく身につけ、演習で確認・アウトプットする設計が本書の強みです。
入門英文解釈の技術70の使い方をノートの書き方まで完全解説!
『入門英文解釈の技術70』は、ただ読んだだけでは力がつきません。構文を「自分で取る」→「自分で訳す」→「解説と照らし合わせる」というプロセスが重要です。
おすすめの学習方法
SVOCを意識しながら例文を読んで、主語・動詞・目的語・補語などを自力で区別してみましょう。
模範訳を見る前に、自分なりの訳文を紙に書き出します。訳しながら構造を再確認する意識が大切です。
NG例:頭の中で訳して答えを見て「なるほど」で終わる
本書の解説ページでは、構造・文法・意味が丁寧に説明されています。自分の訳とのズレを確認しましょう。
なぜその訳になるのか? を考えると理解が深まります。
なんとなくではなく訳がどの英語に対応するのかを確認しましょう
例題と同じ構文を使った練習問題に挑戦。例題で学んだ構造が「初見の文」にも適用できるか確認します。
正誤チェックと、なぜ間違えたのかを一言メモ。
できなかった問題には×マーク、不安な問題には△をつけることがおすすめです。
ノートの書き方例
1題ごとに以下のような構成でノートを作るのがおすすめです:

復習方法(重要)
解きっぱなしにせず、構文が「再現できるか」を確認する復習が非常に大切です。
「できた問題」も必ず2周目でSVOCを振り直し、和訳を再現できるかをチェックしましょう。
1回で覚えたつもりでも、構造理解が浅いことは多く、見直すことで理解が定着します。
復習ステップ例
まず、例文を音読してみて構文や訳が考えられるか頭の中でチェックしてみましょう。
- 1周目でミスした問題:必ず構文+訳をもう一度ノートに
- 1周目で正解だった問題:SVOCを振って、訳せるかだけ再確認
復習のタイミング目安
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 翌日 | 前日解いた問題の復習(記憶の定着確認) |
| 1週間ごと | 間違えた問題に加え、1周目で「不安だった問題」も再確認 |
| 1周終了後 | 間違えた問題を中心に1周目に正解した問題も確認 |
復習時は「構文を見抜けるか」「意味を取れるか」の2点を再確認。
なんとなくではなく、「論理的に」訳せるように学習しましょう。
ここで差がつく!音読・シャドーイングで定着させよう
本書は例文すべてに対応した音声(CD or mp3配信)があり、音読・シャドーイングによる構文の定着にも役立ちます。
- SVOCを意識しながら音読する
- 和訳を思い浮かべながらシャドーイング
- 英文→構文→訳の順で「読める感覚」を養成
読むだけで終わらせていませんか?
『入門英文解釈の技術70』は、構文を見抜く力をつけるための参考書ですが、「読んだだけ」で終わってしまう人も多いのではないでしょうか。
構文を理解しても、それを実際の英文読解や試験で活かすには、頭の中だけでなく「身体で覚える」プロセスが必要です。
そこでおすすめなのが、音読とシャドーイング。
構文学習と並行または復習として行う音読・シャドーイングの活用法を、具体的なステップ形式で解説します。
音読・シャドーイングで何が変わる?
- 構文が「見える」だけでなく「自然に読める」ようになる
- 英語の語順感覚、修飾関係を感覚でつかめる
- リスニング・スピーキング力にも直結
- 模試や共通テストの読解スピードが大幅アップ
特に『入門70』のような短文の構文教材は、音読・シャドーイングとの相性が非常に良く、1文1文の理解を深めるには最適です。
音読のタイミングはいつがベスト?
| やり方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 構文学習と並行 | 毎回定着しやすい | 音読に慣れている/毎日時間が取れる人 |
| 1周目終了後にまとめて | 忘れかけた頃に復習として効く | まず一通り解き切りたい人 |
具体的な音読・シャドーイングのやり方
上記で説明した、おすすめの学習法で構文学習を終えた文章に対して、次のステップで音読に取り組んでください。
- 英文を音声にあわせて音読(ゆっくり3回)
- 意味を思い浮かべながらシャドーイング(2〜3回)
- 再度構文と訳を確認 → 必要があればもう一度音読
シャドーイングで意味が出てこない部分=構文理解が甘い箇所
構文の理解 × 音読の習慣 → 読解力・語順感覚・リスニング力の底上げに直結
音声付きの構文参考書は、音読を活用してこそ真価を発揮
1日1題、5分でもOK。
読むだけで終わらせず、「読める英語」を「使える英語」へ!
具体的な学習スケジュール(月毎・日毎)
『入門英文解釈の技術70』は、約2ヶ月で完成させるのが現実的かつ効率的です。
目安としては
1ヶ月目:例題+演習で70題を1周
2ヶ月目:間違えた問題を中心に2周目+構文復習+3周目で完成へ
月間スケジュール(2ヶ月で完成)
| 週 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 1週目 | 構文パターン1〜18(例題+演習) | 1日3〜4題 |
| 2週目 | 構文パターン19〜36 | 1日3〜4題 |
| 3週目 | 構文パターン37〜54 | 1日3〜4題 |
| 4週目 | 構文パターン55〜70+1周目の復習 | 復習も含めて調整 |
| 5〜8週目 | 2周目+苦手構文の集中復習 3周目で完成まで学習 | 1日5〜10題の確認ペース |
日別スケジュール(平日中心型)
学校と両立する場合は、平日に例題・週末に演習や復習をするのがおすすめです。
| 曜日 | 内容 |
|---|---|
| 月〜金 | 例題3題/SVOC+訳+解説チェック |
| 土曜 | 例題の演習問題に取り組む(15題分) |
| 日曜 | 演習の間違えた問題を復習・記録 |
学習のポイント
- 1周目は「解く → 構文確認 → 訳す」の基本動作を習慣化
- 2周目は「構文が見えるか」「訳が再現できるか」の確認中心
- なんとなく訳すのではなく論理的に訳すことを意識
構文把握の力は、毎日少しずつの積み重ねで必ず伸びていきます。
「毎日1題」でもOK。続けることが最優先です。
次におすすめの参考書
『入門英文解釈の技術70』で構文読解の基礎を終えたら、次は志望校や目的に応じてステップアップしていきましょう。
続けて解釈系の参考書を学習するよりも同じレベルの長文問題集で実践形式の演習を積むことをおすすめします。
学習した構文の取り方を実際の入試問題で活用することによって知識を使えるものにしていきましょう!
構文の知識は問題演習で使ってこそ本当の実力になります。
文構造を意識しながら長文を読む練習に進みましょう。
実践編:同レベルの長文問題集(おすすめ3選)
| 参考書 | 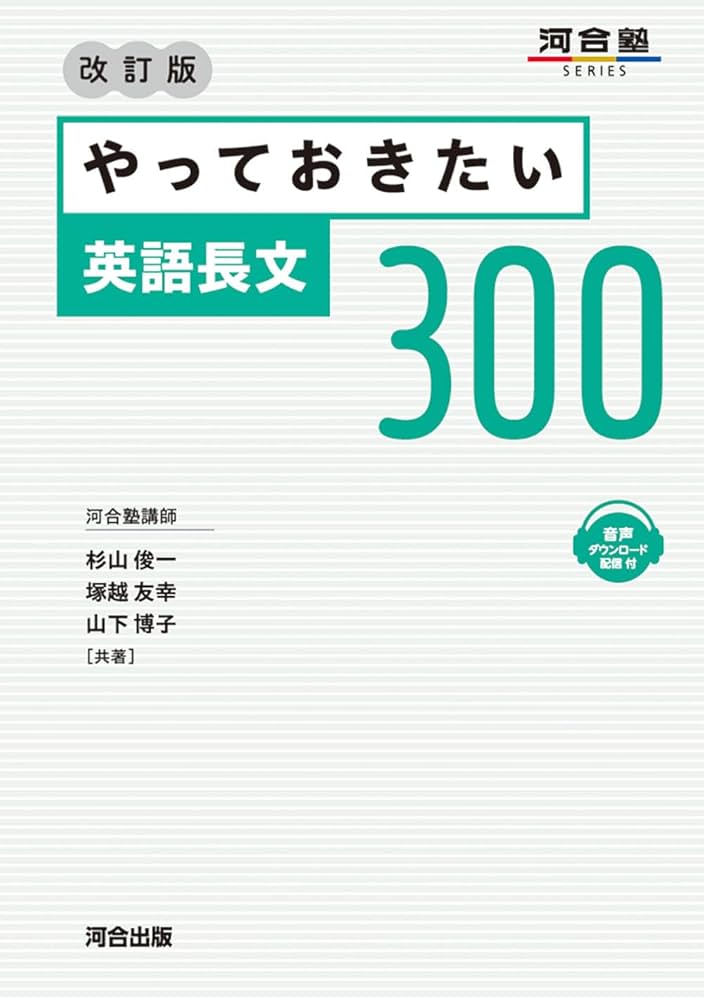 |  |  |
|---|---|---|---|
| 教材名 | やっておきたい英語長文300(河合塾) | 英語長文レベル別問題集4・5(東進ハイスクール) | 毎年出る頻出英語長文(桐原書店) |
| 特徴 | 1題約300語。難関への登竜門的な定番 | レベル別で無理なく進めやすい。構文復習にも◎ | 入試頻出テーマの演習+文構造がとりやすい設計 |
| 対象レベル | 偏差値55〜 | レベル4:55前後〜 レベル5:60前後〜 | 共通テスト〜MARCH |
これらの長文集で、構文を見抜く練習をしながら読解のスピード・精度も高めていきましょう。
発展型:さらに構文力を伸ばしたい人へ
上記の長文問題集が問題なく出来る場合や、難関大学で記述式の和訳問題が出題される人には、以下のような構文解釈書がおすすめです。
構文の学習に並行して長文問題集にも取り組んで得点を伸ばしていきましょう!
| 参考書 |  |  |
|---|---|---|
| 教材名 | 基礎英文解釈の技術100 | ポレポレ英文読解プロセス50 |
| 特徴 | やや長めの例文で構文+論理の読解練習。同シリーズなので引き続き学習しやすい。 | 難解な文法・構文・論理のトレーニングに特化。 解説が端的なので注意。 |
| レベル | ★★☆ | ★★★ |
| 対象 | MARCH〜地方国公立〜旧帝大中位 | 早慶・東大・京大など |
演習と構文の両立が不安な場合は、「平日=構文、週末=長文」のように曜日で分けるのもおすすめです!
まとめ
『入門英文解釈の技術70』は、英文を構造から読み解く力を身につけたい受験生にとって、最初の1冊にふさわしい参考書です。
- 文構造(SVOC)を意識して読む「型」が身につく
- 全70題を2ヶ月で無理なく学べるスケジュール
- ノート・復習・音読を組み合わせて定着率UP
- 学習後は長文問題集で実戦練習 → 構文力の活用へ
「構文が見えるようになる」と、長文の読み方が変わります。
読む手が止まらなくなり、訳すことが楽しくなります。
最初は慣れないかもしれませんが、1日1題からでも十分効果があります。 英文を“正しく読む力”は、すべての読解問題の土台になります。
ぜひこの1冊を丁寧に仕上げて、次のステップに進んでください!
戦略的な学習ならオンライン学習管理塾の168塾がおすすめ
「1人で毎日の学習を継続することが難しい…」と感じる方は、168塾のサポートを受けてみませんか?
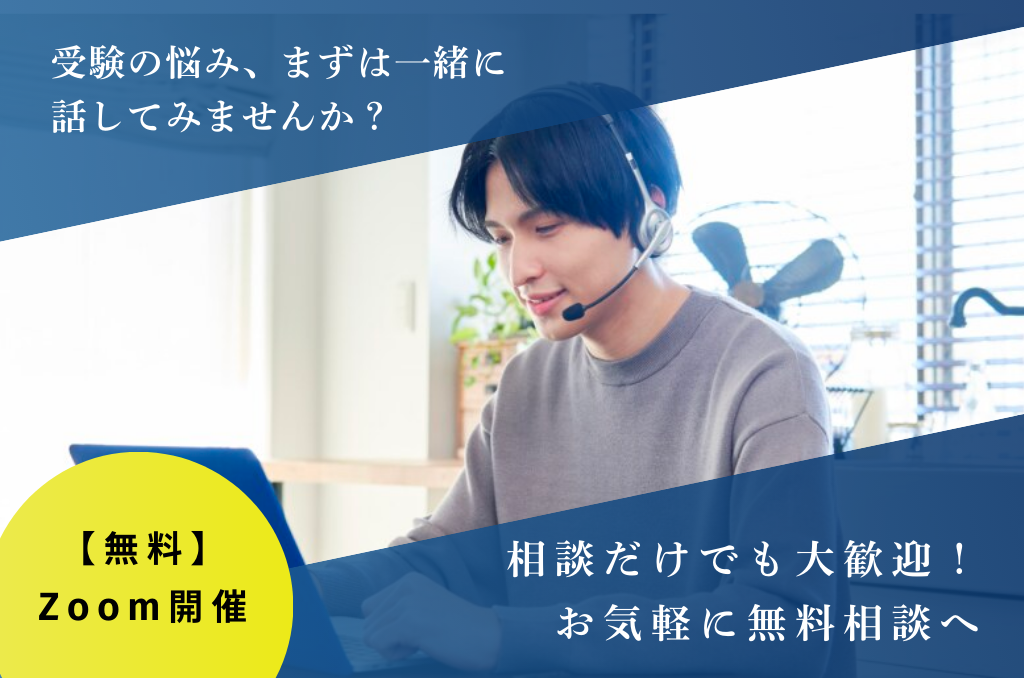
 ライター
ライター168塾では、専用の学習管理アプリを使用して、学習計画作成と徹底した学習管理の指導をうけられます。学習の方針で悩んでいたり、自力で学習継続が難しい人におすすめです!
- あなた専用の学習計画 × 週次面談でサポート
- 毎日、応援アドバイスで勉強習慣定着を徹底サポート
- 学習戦略プランナー×学習管理コーチのW指導体制
\今の勉強法で大丈夫?プロがあなた専用の計画を作成!/